寄稿・投稿
著作
- 幕末における科学思想
幕末における科学思想
(変革を準備したものとしての科学)への一考察・・・正徳元年(1711)越後村上・安房北条・周防。同二年加賀大聖寺、同四年武蔵小金井、享保二年(1717)伯看・因播・備後、同三年備後、同四年周防岩国、同五年紀伊、同十一年但馬生野・信濃上伊郡・越後東頸城、同十二年美作津山領、同十四年岩代伊達郡、同十七年伊予・出雲、同十八年飛騨高山・丹後加佐郡、江戸・伯耆の坪上山、同十九年伯耆・安芸・肥後、元文三年(1738)磐城岩手・但馬朝来郡、同四年但馬・因幡・美作勝北郡、寛保二年(1742)伊予砥部・肥前東松浦、延享三年(1746)磐城、同四年羽前・伊予大州、寛延二年(1749)幡州姫路・岩代安積郡・佐渡・岩代金曲、岩代伊達郡桑折・甲斐、同三年讃岐九亀・伊予大州、宝暦元年(1751)土佐佐川、同三年備後福山領、同四年筑後久留米・伊予西条・美濃郡上郡・大和十市郡、宝暦五年陸中・羽後・出雲広瀬・和泉・・・一揆続発。
天明七年(1787)米価謄貴。一部問屋・株仲間、会所を解散する。同八年幕府、御用達町人に対し拝借金の返納を命ず。寛政一年(1789)旗本・御家人の負債を減免・貸金会所を設置・大阪米蔵の納宿を全廃。寛政二年旧里帰農令公布・米方御用達起る。寛政六年寛政元年施行の倹約令を十年延長。文化六年(1809)江戸の十組仲間の出金で三橋会所設立。同十年三橋会所経営の米立会所設立・・・。
元文四年(1739)ロシアスパンベルグ探検隊三陸海岸・房州沿岸に出没、日本船と交易。正徳元年(1711)千島列島の第一島を経略。明和五年(1768)エトロフ島をロシア領に編入。明和八年ロシア人ベニョウスキーよりロシアの日本侵略計画伝えられる。天明三年(1783)工藤平助「赤蝦夷国説考」を著す。同七年林子兵「海国兵談」を著す。寛政四年(1792)林子兵、処士横議の罪で処罪さる。同四年ロシア使節のラスマン根室へ来航。同八年イギリス人ブロートン室蘭へ来航。同九年ロシア人エトロフト島に上陸。享和三年(1803)アメリカ船長崎来航、文化一年(1804)ロシア使節レザノフ長崎へ来航・・・。
幕末、それは無類の絶対を誇った封建権力が、打ち続く飢饉と重税に喘ぐ百姓の蜂起の波、富を蓄えていった町人の抬頭、開国を迫る外敵の圧力、あるいは支配の権威の学を否定する事実志向の学問への情熱等によって、その根底から、間接に直接にゆるがされ、新しい時代への息づまる期待とともにその矛盾をさらけ出し、変革へなだれこんでいったそのような時代であった。
「天下を治むと云ふは失いなり。自然には乱も無く、治も無く唯直耕安食安衣あるのみ。不耕貧食して直耕者に救われながら、民を治め、衆生を救ふなど云ふは、履を冠して笹を?くの逆言大罪なり。」
マルクス、バクーニン出現の約一世紀半前、日本の歴史上、自然世の生活をその思想の根底に据え、強固な封建体制下、独自の共産制社会を打ち出した埋もれた一思想家がいた。安藤昌益。
彼が生きた時代は元禄から宝暦にわたり、主だった数だけでも百にも及ぶ一揆、打毀しが続発していた。当時は、儒教思想によって自然が規範的、静観的に人間を規制する身分的秩序原理として把えられていたのに対し、彼の思想は身分制度のみならず、政治、経済構造、宗教、医学、本草、物理等のあらゆる分野にわたり、すべて自然に対する深い洞察から出発し、「互性活真」(活きた自然の事実から、相対的に存在する萬有の性質=原理)に包括し、人間の真の生活を直耕直食としたのである。
彼は子弟たちを北海道から九州に至るまで(松前、八戸、秋田、須賀川、江戸、伊勢、大坂、京都、長崎)散在させた。彼らは医者であったり、薬屋であったり、代官であったり、いわゆる陽忍であった。昌益を中心にした思想の実践は、当時の情況下でいかに危険なものであったかは推察できる。彼らの行動が地方のさまざまな地点で打ち喘ぐ農民を中心とする下層民衆に一つ一つ確実に、生きる糧を生えつけた。そしてまた寄せては返す波の如く次第に高まりゆく一揆。打毀しを支えるには、おそらく名もない幾多の昌益が存在していたはずである。
この時代はまた、幕臣、武士、浪人、医者、商、町人・・・さまざまな階層の人々が自らの知的欲求を貪欲に伸ばしつつあった。
今日に続く明日が、今日と変わらぬ明日であること、それがあたりまえとして在った身分秩序体制下、商品流通形態、交通形態の変化に伴う経済構造の変化は現象的次元から確実に人々の日常生活に於ける意識構造へと波及していった。
時は蘭学勃興期、江戸、京都、大阪、長崎を中心に諸科学実践の現実的基盤たる数多くの塾が形成されていった。その中心的存在に、杉田玄白の弟子大槻玄沢が起こした芝蘭堂があった。ここでは蘭学を通して、医学、天文学、薬学、物理、化学等諸科学知識の交換が行われ、京都、大阪付近からこの塾に席を置きその情熱に触れ、知識、実践方法を吸収し、自ら地方へ散って新たな運動の核としての塾を起す者も少なくなかった(小石元俊による京都の辻蘭堂、橋本宗吉による大阪の絲漢堂等々)。
塾に於ける運動は、幕末時代状況が生む必然的帰結として、医学関係者のみならず、田村藍水、平賀源内らの物産家、クナシリエトロフ島を探検した近藤重蔵、林子兵、工藤平助、洋画家司馬江漠等多くの市井の人間をもその渦中に巻き込みながら幕藩体制批判、経済構造、政治機構にまでも上昇していった。
そして、これまでの封建体制の諸矛盾をあばき出し、儒教支配による知識の独占をも打ち破り、諸階層、特に庶民の側の精神構造へと影響していった。
飢饉で常に苦しむ農民は、その生命を保つために天候を予測し、天災に備える方策を必要とした。この必要は“農業全書”の著者、宮崎安貞、サツマイモの青木昆陽を生み、天文、歴学、地理学を育てた。商品経済の発達につれ、量を知ることが数学、測量学を発展させ、全国実測図の伊能忠敬を、博物物産の学などを次々と生み出していくのである。経験をまとめあげていったこれらの自生的学問は次第に理論家への欲望を喚起し、未知への挑戦は全てを投げ打って進んでいく底知れぬ活力にあふれ、医学を中心に広範な展開を繰広げていくのである。
宝暦四年(1754)二月七日、京都郊外の刑場の片隅で三十八歳の男の首なし刑死体の解剖行われる。同八年長州萩、京都伏見、同九年萩で日本初の女体解剖、明和七年(1770)京都、そして同八年三月四日千住小塚原で・・・。名古屋玄医、後藤昆山が唱えはじめ香川修徳、吉益東洞、山脇東洋などがその大成者とされる古医方の人々には、医学での実証精神を鼓吹し、その主義に徹して自らの経験に徹しない限りは、いかなる古来の権威をも認めないという科学精神の発芽はあった。古来からの五臓六腑説に強い疑いをもっていた東洋は人体の正しい構造、機能を内部に及んで知ることによってはじめて病いは完治できると主張し、人体の内景を見ることを待ち望んでいた。彼の疑問は、カワウソの解剖によっても晴れることはなかった。刑死体の解剖は官の制するところであり、儒教が思想界を支配し、封建体制を支えていた当時、「受刑死体であろうと死体を解くことは、残忍極まりない行為であり、君子の道に反する許されざる悪行」であるとか、「死体の臓器をみても生体の病を治すには役に立たない」という激しい非難の中で東洋らは覚悟をきめ、公許を懇願し、京都所司代酒井忠用から許可を受けここに日本初の人体解剖は行われたのである。人体を知ることは東洋らにとって何にも増して必要なことであった。これに刺激され刑死体解剖の火の手が上がり後に解体新書を訳出した杉田玄白、前野良沢を決定的に動かすことになる。儒教思想は学問への欲求の前に東洋らを支配しきることは出来ず、また、権力も彼らの覚悟に裏打ちされた医学の前に公許を余儀なくされたのである。このことは、ごく小さな事ではあるが完全を誇っていた意識支配の網を微力であるが確実に破っていくことになるのである。
備前岡山池田家の家来鈴木の総領旭山武士を捨て町医者となる。宝暦十二年(1762)平賀源内祿を辞す。明和六年(1769)麻田剛立脱藩。弘化四年(1847)豊後日出藩元家老帆足万里脱藩上京、被支配者の肉体と精神に対し、極限にまで自らを絶対者として貫こうとする封建体制下にあって、脱藩は忠誠を破るものとして自らが規制し、又、切腹を命じ、さらに悪事をした脱藩者には打首の重刑を課する厳しい掟があった。
内部矛盾をかかえ、切腹をも覚悟し、また身分として安定していた武士を捨て、家を捨て、自らの理念にまっしぐらに突き進んでいった彼らを支えたものは息づまるような“変革”“究明”へのさまざまな期待であった。意識し、あるいは意識しなかったにしろ、彼らのこうした事実への志向が人間の主情的世界から肉体的構造へ、そしてさらに人間を包む物理的、空間的世界へと拡大するにつれて、彼らの行為は着実に伝統的儒教の呪縛から自らを解放し、新しい時代の意識構造をつくり上げていくことになったのであり、科学のもつ具体性、事実性、実利性そのものに対する驚くばかりの発見が封建体制の絶対性をゆるがせ、彼らの内部に権力がみだりに立ち入ることのできない領域をつくり出していったのである。
- 雪が舞う東北の地への風信
雪が舞う東北の地への風信
1970年 会社同期会誌「むくの声」第4号に投稿 小波 淳(ペンネーム)
わたしがおまえのすむ(かつてわたしもすんだ)土地を離れてからもう二度目の冬を迎えようとしている。
かって、離れるに際しわたしの幼さをむきだしにして おまえに迫ったものだった。そのしぐさの幼さをしっ たわたしではあったが、思いつめてまた同じようなことをやってしまう最近のわたしであることを思うとき、 わたしがわたしとおまえの関係を”対なる幻想”という領域で対象化しようとしていることも、結局はまだ まだ未熟なものであることを思うのだ。わたしに関する領域がそのままおまえのものへ、そしておまえに 関する領域がとりも直さずわたしのものへという地続きの関係性を現実的たらしめる方法論を獲得する にはまだまだお互いに幼いようだ。もしかしたら、それは方法論などと規定する必要のない、男と女の 間にときたま交わされるあの言葉にならないものにかかわることなのかもしれない。
先だって、めずらしく上京してきた兄と、若干の気恥しさを覚えながらおまえとわたしの関係を語り合え る一夜をえられた。そのときもやはりわたしたちがまだまだ未知の関係にあり、おまえを包括しうるわたし の空間の未熟さを思った。それはおまえにとってもいえることだろう。最近短かい文章を読んだ。その中に、ある一組の夫婦の存在のし方についてのべている部分がある。 少し 長くなるが書きとめておこう。
—-山の中で夫婦二人きりでくらしていればこうなるよりほかないとおもわれるように、今日ついた ばかりの眼にもふたりの間が温かくすっきりと疎通していることがすぐわかった。(中略)そして高地の せいか、夫婦のどちらにも粘着するようなものはなく乾いてさぱさぱしているのも、わたしの眼には愉 しかった。息子は出征していて、いまはこの宿の並びに家をつくって自給しているといったことが、 その夜いろり端できいた夫婦の身上であった。この夫婦は忘れがたい印象を弱年のわたしにのこした。
いろり端には、ときどき鼠がちょろちょろ出てきて、うろうろ餌になるものをさがしている様子だったが、 驚いたことにわたしたちがいてもすこしも怖がらず、夫婦も追い払おうとしなかった。 〈こんな山の中ですから鼠も家族みたいなもので〉といいながら、丁度飼い猫にいうように奥さんがとき どき〈すこしあっちへいっておいで〉と鼠のほうへ声をかけ手で追うしぐさをする。 奥さんにしいて追い払うつもりがないので、鼠のほうも逃げる気はないらしい。どこかへ引っこんでは、 またちょろちょろあらわれるのだった。ああこの夫婦はいいな、この主人の声はすんでいていい声だ、 この奥さんは親しそうでいて粘りっけがなくていい。そういう夫婦もこんな山の中だからこそ在りうるの だな。おれたちはどうせ戦争で駄目だが、こういう夫婦に偶然であったことはおれにはどんなにこの世の 土産になるかもしれない。
わたしはしきりにそんなことばかりかんがいていた…
–吉本隆明「自立の思想的根拠」-ひとつの死よりー
この文章からおまえがなにを想うかわからないが、ごく平凡ないわゆる庶民ともいえる夫婦の関係に 対する一人の人間の感性が、そして共感が書かれてあることはわかると思う。
この風信を書いている今、ラジオのニュースは今日の事件(三島由紀夫の割腹自殺)を報じた。
一瞬嘔吐を覚えた。それが何によるのか今はわからないけれど引用した文章の著者と同じく、夫婦の 在り方に共感する自分と、三島という一人の著名な人間の死に嘔吐を覚える自分・・・・。
わたしにとっては明らかに(仮にその夫婦の死がわたしに報じられたとして)山の夫婦の在り方のほうが 重たいと感じられる。たしかに三島の死は〈詳しいことはわからないので何ともいえぬが) このようにも人は死ねるものかということで衝撃を覚える。しかしそれがわたしの「人が生きる」ということ に対する思想的次元にまでくい込むものではない。山の中の夫婦の在り方のほうがより基底部において わたしとつながっているように思えてならないのだ。
人は何によって生きるか〈生活するか)。また死にうるべきいかなる理由をももちうるのだろうか。
三島の死は死にうるべき理由を持った(?)一つの例といえるのかもしれない。それにしてもあまりに直戴すぎはしないか。私には生きる過程も死に至る過程〈死に過程もくそもないといえるかもしれないが) も、もっとゆるやかなじっくり煮つめられていくべきもののように思えるのだ。また、生き抜くことに 自らの全存在を投入していく過程はいかなる名目を伴った死などよりも得難く思える。
三島の死が人々にどのように影響するかはしらぬが、人が生活のレベルを他から影響をうけるのは、 日常の現実性、具体性を通じて昇華されたもの、また逆過程をたどれば人の日常の基盤となるもの 〈=思想)からであると思えるのだ。
まだまだ幼いわたしたちはさらに多くの生活者からその過程を学ばなければならないようだ。
おそらく、人間が一人から二人に、さらに二人からより多人数へとその関係を拡げていく過程には、 拡がる度合に応じて多くのものが抜け落ちていくはずだから・・・・。
一つの死を契機に、最初に書き始めたことからだいぶそれたように思うが、一九七〇年十一月二五日 現在わたしが思うことはこんなことである。
これから訪づれる長い冬を想うとき、東北の地の風土は少なからずわたしの精神形成に影響してい るようだ。より暖かいこの地にいて囲りは冬とはいえど明るくなごやかだが、わたしの心は 雪の舞う東北の地にいるのとたいして変りはない。
・文化・スポーツ活動の発展のために
文化・スポーツ活動の発展のために
1968年大学工学部新聞に投稿 小波 淳(ペンネーム)
昨年の学生大会が流会となり、新執行部の基本方針、活動方針が決定しないまま現在に至っている折、今年度の学友会活動はどうなるのだろうという不安を持たざるを得ない。しかし執行部は動いている。一体何に基づいて動いているのだろうか。新入生歓迎行事にしても、文化・スポーツクラブを無視した歓迎合同実行委員会の設立、そしてその内容といえば昨年度とほとんど同じ。昨年度も感じたことではあるが、執行部は新入生歓迎の意味(私達三年・四年生にとっての、新入生にとっての)がわかっていないのではあるまいか。映画(ミュージカル・恋愛物)、ダンスパーティ、 ハイキング・・・・・と、お遊び行事とでもとらえているのだろうか。東京都立大教授の講演会ひとつだけが何かしら異種に思えた。執行部の人達は講演の内容が私達にとって適切であり、良かったと総括しているが、
ハイキング・・・・・と、お遊び行事とでもとらえているのだろうか。東京都立大教授の講演会ひとつだけが何かしら異種に思えた。執行部の人達は講演の内容が私達にとって適切であり、良かったと総括しているが、 私達にその内容がどのようにかみ合い、そしてどのように良かったのか、欠点は、又これからの私達の行為にどう結びつくのかという展望まで語らなければ総括といえないだろう。手放しで喜んでいる時は、その背後に必ず陥し穴が潜んでいることを知らなければならない。私が思うに、新入生を歓迎するということは、少なくとも現在当工学部学生が抱えている問題から、大きくは私達を取り巻く現状況において私達が一個の人間として問題にしなければならないことを新入生に提示し、話し合い、これからの学友会活動に対する意識を高めることではないだろうか。執行部が口癖にしている民主主義、学内の統一と団体、etcはこれからの行事の中のどこに顕われているのだろう。ダンパの会場にだろうか。合ハイにだろうか。さらには、サークル活動の活発化を口にしながら、サークルを無視した実行委員会設立をやっている事実をどうとらえたらよいのだろうか。ひじょうに疑問を持たざるを得ない。
私達にその内容がどのようにかみ合い、そしてどのように良かったのか、欠点は、又これからの私達の行為にどう結びつくのかという展望まで語らなければ総括といえないだろう。手放しで喜んでいる時は、その背後に必ず陥し穴が潜んでいることを知らなければならない。私が思うに、新入生を歓迎するということは、少なくとも現在当工学部学生が抱えている問題から、大きくは私達を取り巻く現状況において私達が一個の人間として問題にしなければならないことを新入生に提示し、話し合い、これからの学友会活動に対する意識を高めることではないだろうか。執行部が口癖にしている民主主義、学内の統一と団体、etcはこれからの行事の中のどこに顕われているのだろう。ダンパの会場にだろうか。合ハイにだろうか。さらには、サークル活動の活発化を口にしながら、サークルを無視した実行委員会設立をやっている事実をどうとらえたらよいのだろうか。ひじょうに疑問を持たざるを得ない。このような折、最近わたされた学友会誌に「炎」編集委員の名で“一層の文化、スポーツ活動の発展のために”というサークル論が載っているのに気付いた。この文に対して少々の不満や疑問な点を感じざるを得なかったので、私のサークルに対する考えをおりまぜながら述べてみたいと思う。
「炎」の人達は流会に終った学生大会において提出された対案書の中のサークル論に対して書いている。まず、クラブ・サークル連絡協議会準備会が結成された時にサークル論・運動論がないといってその不明確さを指摘した人達を誤っていると書いている点から述べなければならない。
何ら方向性、運動論の欠如した運動において何かを為しえた例があるだろうか。何かとは何十項目かの要求を勝ちとるとこではない。こういった要求はあくまでサークル活動をささえるものではあっても活動内容ではないはずである。運動論の不明確さという本質的な点を指摘したのに感情的な理由(実に本質的でない)でかたずけることは絶対に間違っている。もっと謙虚にならなければならないのではないだろうか。そして又勝ちとった要求から現在のサークルにおいてどのような活動がなされているかといえば、以前と変わらない、いや以前よりも低迷した活動が存在しているだけである。勝ちとったという成果を「炎」の人達や執行部は後生大事にしているが、現在のクラ連協が何をしているといえるのか。もちろんクラ連協の存在は有った方がいいし、有るべきものと思われるが、だからといって要求を勝ちとるだけの形骸化した有名無実の協議会であっていいはずのものではない。
「我々のサークルの意味は趣味でもなければ娯楽でもない。そして単なる人間関係、友人を求める機会を得るためでなく、又社会に出たら役立つ様な先輩、後輩の関係を、付き合い方を、協調の精神(?)を学ぶものではない」という文にどんな侮辱があるといえるのか。まさに当工学部サークル活動の大半に当てはまる問題点ではないのか。私達の周囲の現実に目を向けずに何ら危険のない温床でぬくぬくとしている活動は絶対サークル活動とは認め難い。真にサークル活動で何かを創造し、止揚していくためにはこのようなべったりした人間関係を取り去り、裸で向き合った人間同士のはげしいぶつかりが必要である。
フォークソングに関する所を読んで私は笑ってしまった。要約すると、「ジョーン・バエズはフォークソングを歌って反戦運動をしており、フォークソングはべトナム反戦と共に広まった→日本にもフォークソングが流行している→日本のフォークソングもりっぱな反戦運動をしている」と「炎」の人達はいっているが、私がここで指摘するまでもなく、明らかに誤った破論法と言える。確かにジョーン・バエズは反戦歌(?)を歌い反戦運動をしている。だが日本のフォーク界では反戦の反すらも見い出せない現状ではないのか。さらに、バエズの反戦行為に関して問題にするときは彼女の行為のあり方、内容を問題にすべきであって表面にあらわれたことで判断するのもおかしいことである。そして、ひとつの例が全てに当てはまるという倫理の誤りは小学校ですでに教えられていることである。かの有名な森山かよ子ですら、「バエズは尊敬するが、私は反戦歌は歌いません」といっている。少なくとも
 の日本のフォークソングは、映画「日本春歌考」(大島渚作品)において扱われている程度のものでしかないことは明らかなことである。
の日本のフォークソングは、映画「日本春歌考」(大島渚作品)において扱われている程度のものでしかないことは明らかなことである。運動部について同じようなことがいえる。現在の工学部の運動部をサークルという観点から考えるなら対案書に書かれてあった「その機能はいたずらに栄養超過の、そして欲求不満のはけ口として存在するのではない」ということは間違っていない。しかし私が見る限りでは現在の運動部はサークルの機能は持っていないと思う。「炎」の人達は運動部の人達が一体どのような犠牲を払って活動しているといいたいのだろうか。私には我が身体を鍛えるためと、べったりとした人間関係のための犠牲であるとしか考えられない。もし運動部も対案書でいっている意味で、又私のいう意味でサークルであるとするなら、少なくとも独自の運動論が存在しているはずだが私はまだ聞いたことがない。
「民族的、民主的文化、自主的民主的学問研究、自主的、民主的スポーツを求め、創造的科学的精神を養い、健康で明るい学生生活をめざすことは学生にとって切実な具体的な要求である。」・・・・・よく並べたものだと感心させられる。余程民主、自主という言葉がお好きらしい。それはいいとしても、当工学部に「炎」の人達と同じ考えを有する方々の執行部が誕生
してからどのような民主云々が生まれたというのだろうか。民主的文化、民族的学問研究、民主的スポーツetc・・・・・これらは一体どのようなものなのだろうか。具体的な要求どころか全く抽象的な言葉ではないのか。第一、現実へ対処しようとする者にとってその前途は民主的云々の羅列で解決できる程明るいものではけってはないはずである。もっと現実を見つめなければ「炎」の人達のいう現実(社会)を変革することはできないだろうし、そして又現実の穢さ暗さにもっと絶望し、その中から這い上ろうとするエネルギーころが現実変革に群がるものだと思う。ベトナム云々いいながらのダンパや合ハイのようなレクリェーション的集りからはけっしてこのエネルギーは生まれないことは確かである。
御苦労なことに、サークルをイからチまで分類しているが、どうも運動体としてのサークルとただの集団をごちゃ混ぜにしているようだ。第一、サークルを手段、目的で分類すること自体おかしいと思う。このような非生産的なことはやめた方がいいと思う。サークル論は分類することではなくサークルの在り方や、やっていることを問題にすべきである。楽しみのためのサークルはそれとして認められるのではなく、それはあくまで楽しむための集まりであってサークルではない。サークルとして考えられるのはどのような手段、目的のサークルであれその根底に共通したサークルの意義は存在するのです。そして集まった人達が独自の運動をサークル内で、さらにはサークルの外の現実へ向けていく運動体としてのサークルのみが現実変革のエネルギーを包含しうることは明白なことである。
グリーなどは新入生歓迎オリエンテーションにおいて、「私達のサークルは歌って楽しむ集まり」といっている。これは自らサークルとしての持ち得る機能を捨ててしまったものと見做して誤りはないだろう。私が見る限り、工学部内でわずかにサークル的に活動していると思われるのは社研と写真くらいである。しかしこの二つのサークルとしてその内部における運動もさることながら、とくにその運動をサークルの外側へ向けて展開していく所に多くの問題があるように思われる、つまりサークル内での考え、方法が外へ向っては強力な力となっていないということである。しかしながら少なくともサークル内で真剣に自己の問題に取り組む姿勢に、運動体としての可能性の一端が見い出せるだけでもこの停滞した工学部サークルにとって貴重であろう。
私がこのように反論してきた点を考えてみて、「炎」の人達が反動勢力、分裂主義者呼ばわりする対案書のサークル論に一体どのような反動が分裂工作があるといえるのだろうか。むしろ「炎」の人達が用いる感情的なセクトやドグマが明らかになるだけではないだろうか。私がここでこのことを指摘するよりもっと的確に指摘している文を引用してみよう。
石堂淑郎「映画における幻想と死」(デザイン批評・1968・2・NO・5)より
・ ・・・・中 略・・・・・
つまり、ボーニーとクライド(アーサー・ペン監督“俺たちに明日はない”の主人公達)は、絶望をその両肩におぶったまま譲らず遂に殺され、創価学会・民青はその絶望を宗教的・政治的幻想という偽りの希望に肩代わりさせるのだが、少なくとも前者は精神的な疎外を肉体によってうけとめることによってプロテストしているのに、後者は疎外からより大いなる疎外へと移行しているだけなのである。キエルケゴール風にいえば絶望を絶望としてうけとめて死ぬのと、絶望を希望という名の絶望に肩代わりさせてニコニコするのとどちらがより絶望的であるのか、勿論、後者である。これをいま別の面から考えてみれば、学会なり民青なりの核である宗教的、政治的幻想は敵対者に対する憎悪をその唯一の栄養としていることがあげられる。つまり彼らのニコニコ顔は非同調者に対する憎悪の顔と表裏で一体であることを忘れてはならない。それは幻想という見えざる呪縛の力にとらえられている人間のつねである。
・・・・・後 略・・・・・
「炎」の人達はこの引用文の内容をどのようにとらえられるでしょうか。
「炎」の人達は対案書を部分的にとらえて非難しているが、さてそれはどうすればいいのかという点に関しては、民主的、自主的云々という一般的抽象的言語をふりかざすのでは仕方がないでしょう。これはあくまで非難でしかない。読む方でも戸
惑うし不満を感じて当然です。それに、現在の日本ではどこにも民主的と名のつくものは存在していないと思うし、私には「炎」の人達のいうような民主云々は永久に存在しないような気がします。いやたとえ存在したとしてもそれは真の民主云々ではないと思う。第一、民主主義の原理とよくいわれている多数決の原理ほど暴力的なものはないのですから。最後まで個と個のはげしいぶつかり合いでなければならず、その中で運動を発展していくのがサークルであると思う。
現在、工学部サークル内に巣喰ってっている低迷とマンネリの根本的原因は、サークル員一人一人が個としてのサークルに対する意識を持っていないことにある。つまり、サークルは何を為しうるのか、何を為さなければならないのか、サークルが現実(社会)の中でどのように位置ずけられるのか、サークル員たる個人はいかなる行為をすべきかといった点が迫求されなければならないのである。又自分の生き方に対して何ら疑問や悩みを感じられない(自らの甘さのため)点にもその原因があるだろう。従って現状況において必要なのは、サークルの一人一人が一個の人間として自己への問いかけを始めることである。自己の存在のしかたを疑うことである。
サークルが運動体としての機能を持ちうるのは、前述の行為をなしえたサークル員一人一人が現実の中で抱えている諸問題をサークル活動の中に持込んだ時である。この時にこそ具体的サークル活動(例えば、写真部なら写真を見、撮ること)によってさまざまな問題が提起されなければならない。しかし、現在の工学部のサークルの状況ではそういった問題提起も大部分のサークル存続主義者によって打消されるかも知れない。しかし私達は、サークルはサークル存続のためのサークルではなく、又こういった存続主義者のものでもなく、一個人の意見を消し去っていい理由はどこにも存在しないのだということをそして、サークルを動かしていくのは構成員一人一人であることを考えなければならない。そしてサークルがその機能を持ちえた時、私達のまわりの様々な問題を生ましめている現実(社会)へ向って、真の行為がなされるのである。そうでなければ個人の問題は個人の中で内閉するサイクルを描くだけで終るだろう。そして現実はあいも変らず私達を呑み込みながら膨大に変化し続けるだけである。
現在サークルの問題に取組んでいるある女性はいっている。
『蟻地獄の中にいる蟻と同じ状態ではあるけれど、蟻地獄には死がまっているが私達のは、いわゆる楽な事がまっています。今この手をはなせば、楽になるのだが・・・・・。(でも)いくら振り出しに逆戻りしても負けたくない』と。又他の女性はこういっている。『奇妙なことには、過酷なはずの社会の中には広漠と安易さが広がっているのだが、その中にとっぷりと浸ってしまい、そこから出ようともがくことさえ愚劣であると思わせるような抜け道のないいらだちの中にはまり込んでしまう。そしてこの慣れこそが、生することの中にある歓楽に与えられた極めて凄烈な復讐であるのかもしれなかった』と。この二人のことばには私の内部に鋭く突きささる。このような自己へのきびしい告発の例は、まさに工学部の大半のサークルが、又個人が現状況における自己の問題として真剣に取組まなければならない点を的確に指摘している。そしてもはや個人的な問題から具体的サークル活動を通して一つ一つ解決していく行為を明日といわず今から始めなければならない。しかも、自分でやらなければ他の人は誰もやってはくれないことをはっきり自覚しなければならない。
・ Hへの便り (もしくは不特定多数の他者へ)
Hへの便り (もしくは不特定多数の他者へ)
1970年会社同期会誌「むくの声」第3号に投稿 小波 淳(ペンネーム)
あなたとの通信を絶ってからどのくらいの月日が経っているのか・・・・・、 私にはその記憶を取り戻そうとすれば、かなりの時間を費し、かつてあなたや私や仲間が辿った 足取りを一つ一つ掘り起こさなければならないのに気付く。
そして朧げながらその概要を掴めた際私はあなたとの隔たりが拡大してしまっているのではないか (確信を持って言い切ることができる私ではないのだけれど)という疑問が私の頭に住みついて、 いかようにもがけど、ことさら肝心の時に頭をもたげてくるのです。
私は意を決してこの便りを書くことにしました。私がこのような形(発表という)で人に便りを書くのは 確か二度目です。そう、あなたや私や仲間が詩によって(今から思えば多少の気恥ずかしさを覚えるのだが)当時の”自己変革”を目的としていた折の、最後の詩集に書いたはずです。
『告げる』
ーL子への手紙ー
きみと喫茶店で別れてから幾日経つだろう
君と顔をあわせて言いえなかったことを
この手紙でつたえよう
そうそれはこのような書き出しで始まっていたはずです。あなたが私への便りで”感激の後で くやしくなりました”と語ってくれ、若干の気恥ずかしさをその時は覚えたものでした。
私が今もつきあっているひとが、「最初はあなたが言ったように”告げる”がいいと思っていたけれど、
後 になって同じ号に書いた”帰ることが許されていた時” “旅立”の方に私の姿、心が表れているよう に思った。」と数少ない便りのなかで語ってくれた時、ああこの人もやっと解ってくれたかと、ひとり嬉しく思ったものでした。
『帰ることが許されていた時』
その時
ぼくには帰ることが許されていた
休むことが許されていた
そこは冬ともなれば屋根が隠れるほどの雪に埋もれる
ところだった
ぼくは いま そこにあるぼくを待つ小さなけれど暖かい
保護に向かっていた
そこでは凍付く寒さの中でも ぼくは約束されていた
そこは女が持つあのよどんだ温(ぬくもり)でぼくを
包むかもしれない
そこでは安堵(やすらぎ)と虚脱がぼくを癒すかもしれない
ぼくはそのあまりの歓待に戸惑うかもしれない
けれど それはそんなぼくにはおかまいなしにぼくを
もて遊ぶだろう
ぼくは考えなければならないような気がした
そこがほんとうにぼくの帰るべきところかを
じじつ そこは居心地のよいことは確だった
そして 居心地のよさがぼくの思考を鈍らせていることも
確だった
けれど その確さがかえってぼくの心を不安にし
ぼくは考えなければならなかった
軒に下がる鋭いつららが何であり
暖かくもえさかる炎が何であり
あの温が何であり
そこにいるぼくが許されているかを
『旅立』
右の手には家の温かみを
左の肩にはわたしの思想をたずさえ
わたしの体は右に傾き左に傾く
疲れた足どりで歩むわたしは
どこで倒れるのか
わたしはすでに傷ついている
暗くなまぬるい迷路への旅立ちを
あなたはそらぞらしい他人のことばで止めようとした
わたしはあなたに何ものぞみやしない
わたしの痛む傷口を開くのはやめてもらいたい
あなたにやられるくらいならわたしがやる
できることなら こんな傷はあなたのまえに
捨ててゆきたい
枷かもしれない
白くさえわたる雪道で
長くよこたわるわたしの影は
青白くひかる無数の星の反射にくらむ
そして
黙して歩む午前四時の思考は いま
はてしないサイクルに足をふみいれた
家の温かみとわたしの思想はいま
わたしの内で対立する
けれど
わたしがこのふたつのもちものを
たがいに包含し合うものとしてとらえたとき
わたしは倒れずにすむのかもしれない
今のあなたがこの少しカビ臭く思える昔の作品を、今どのような想いで読み返されるかわからない けれど、”作品には作者の在り方が必ず表出する”といった当時の原則の通り、当時の私自身の姿 が良しにつけ悪しきにつけ現れていると思います。人間ってあまり成長しえないものらしく、今私が あなたに語る私は、当時の私自身と大差なく、同じようなことしか語りえないことに気付き恥をしの< んで持ち出した次第です。
それともう一つの理由は、私が今あなたに言いたい部分の一部を占めていると思うから・・・・。
私がふるさとを離れて横浜に来てから二年目に入ろうとしています。正月に帰った折、Kに会い、 あなたが東京の方に出てきていることを知り、あなたの住所が私がひんぱんに足を運ぶ491の近> くだとわかり、地名を頼りに訪れたのでした。
一年以上のブランクのため(そう、その時はそう思ったのです)あまり話せず、世間話などをしてあ なたの家を去ったものでした。その後何度あなたに電話したでしょうか。その回数が増すごとに、 会った時の頭の片隅に在った、どこか当時とは違うという感じが拡がっていきました。
一方ではそうじゃないと打消しながらも・・・・・。
そして春も近い頃、私はあなたに別れになるかもしれない便りを書こうと思っていました。しかし、 491の原稿、会社の仲間とのやらなければならないこと等に追われ、時間は過ぎてしまっていまし た。そして今、再度あなたに書こうを思ったのです。そう、この前のあなたへの電話が私に決心させ たのです。その電話は、久し振りのKからの便りがきっかけでした。
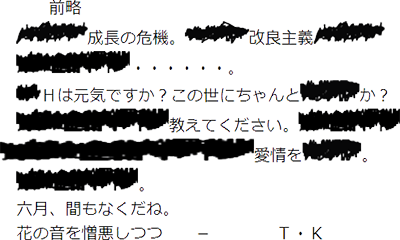
私は彼に書きました。今年あなたと会ってからの経過を、そして感じたことを。折り返しKから返事 がきました。彼もかなり変貌していました。おそらく彼が今属しているセクトの活動を通して勝ち得た 成果なのだろうと思います。
彼の書き出しはこうなっていました。
…僕達がかつて彼女に対して繰返したところのあの詩は書いている?という問には、多分に詩を書 くということ自体を自己目的化しているような感じが在って、僕達自身にとっても彼女にとっても清純 だったとは思いますが、たとえば詩によって表象するという手段で以て先ず自分という存在の皮膜か ら深部へと変革を志向する意志、及び何らかの思想が彼女の頭蓋骨だか脳ミソだかに定着しえなか ったのだとしたら(君の独断であれば重大な喜びですが)口惜しいことだと思います。・・・・・・
またこのようにも書いています。
NIHILISMの美化は愚かだと思います。しかし錯綜した時代状況の中にあって、ひとつの起き上が りは常にNIHILISMの奈落への落ち込みという危機を孕んでいることを考える時、彼女の詩の中に 「モノタイプで鋳造したとて」「とうてい、口、言葉、筆、命とか言うものは浮草のようなもの」「人は人に 別離して・・・・さまよう」という形で表象された或る種のNIHILISMが、一面的にはたおやめ的なおセ ンチを表わしているとしても、NIHILISMを知覚する必要性の尖鋭さとか、不定形の思想をいわば可能 性として僕も多分君も感じていたはずでした。
僕がこの手紙で、私が彼にどんな内容の便りを書いたかおよそ想像できるものと思います。そしてお そらく、私の一昔前の貧弱な隠喩を用いた詩片などより、今の彼の言葉の方が重く響くことと思います。 そしてあなたに電話をしたのでした。何故なら、あなたに対する(普通にすれば他者との関わり方に 於ける)私自身の在り方を彼に指摘されたことと、かつての私(私達)の活動を検討する意味で、やは りあなたに会って話さなければならないと思ったからでした。
その契機が一方的に破棄された時、あなたの声までもが私をさけているように聞こえてしまいました。 そして今、最後になるかもしれない便りを書いていたわけです。
最初に、詩とはいえないけれど私が今書けばその詩の核となるだろう断片を連ねて筆を折ることに します。
ひとりのひとが人間になろうとするとき
無数の秩序がかれを襲う
秩序は造幣局の裏口から
鉄格子の護送車にのってやってくる
そして気づかぬうちに
わたしたちのふところ深くに住みつくものだ
そこに温もりが宿るとき
それは意思ある生きもののごとく振舞い
ひとは自らの内に
新たな秩序を造る媒体を宿す可能性をもたされて
しまう
わたしたちは容易にそれを阻止できない
秩序というものはそういうものだ。
束縛のない留置所の
見えない柵をとりはらえるエナジーは
ひとりのひとにどのような貌(かたち)で訪れるか
ビルディングの谷間に舞うアジビラとしてか
地方の地底の呻きとしてか
闘いはひとりのひとのこころに
どのような貌で想起するか
アトマイズ化されて存る日々の生活の中の核を
集約し変革のエナジーとしてそのボルテージを高め
うる季節(とき)は
ひとりのひとに
どのような貌で
どこから訪れるか・・・・・・・・6/18
追伸
六月十四日はどしゃぶりの雨煙と催涙ガスのたれこめる中、東京の街角を歩いてきました。
最近めっぽう体力のなくなった身体にとってかなりきつい行為だった。 Kもおそらく仙台にてやっているでしょう。彼もかなり身体をダメにしているらしくその苦しさは想像 できるくらいです。
それでは、再びあなたとの便りを交換できるような関係になることを期待しつつ・・・・・・。

